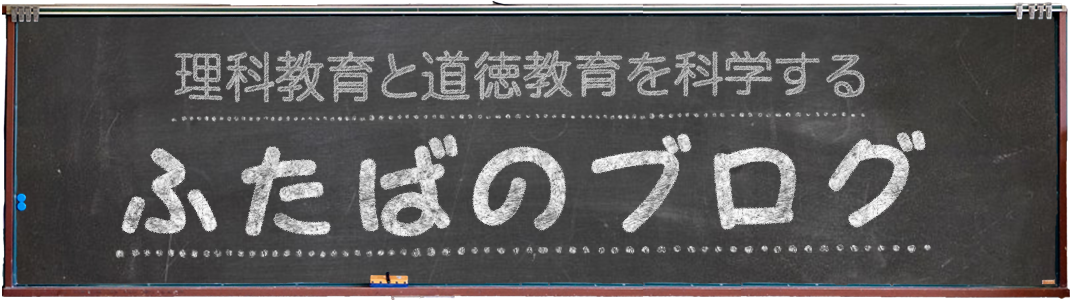色々な岩石の鑑定を行いました。岩石を鑑定するためには様々な方法があります。
岩石鑑定の方法

【主な鑑定方法】
- 硬さ(モースの硬度計)10段階
- 割れ方(劈開、断口)
- 結晶の形(7種類:等軸・正方・六方・三方・斜方・単斜・三斜晶系)
- 鉱物の光沢(金属光沢、ガラス光沢)
- 鉱物の色(条痕色)
- 光学的性質
 条痕板という板を使って硬さを測る方法はとてもわかりやすいです。擦り合わせて傷が行くかどうかで硬さを測定します。
条痕板という板を使って硬さを測る方法はとてもわかりやすいです。擦り合わせて傷が行くかどうかで硬さを測定します。
爪は硬度2です。
18金→硬度3
10円玉→硬度3.5
ガラス→硬度5

釘→硬度5.5
これは傷のつきにくさを表したもので、壊れないかどうかは別問題です。ダイヤモンドがハンマーで割れるのは有名ですね。
- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。
傷のつきにくさということです。ガラスの方がカッターナイフより硬度が高いのでガラス台の上で作業してもガラスに傷はつきません。(カッターの種類にもよります)
色々な鉱物を観察しました。
①石英
水晶の名称で売られています。英語ではクリスタルですね。
真上から見ると六角形の結晶なのがわかります。六方晶系です?
石英の側面の筋は結晶が成長するときにつくそうです。

このような白い石英は、河原に落ちていることがあります。花崗岩に多く含まれています。
②赤鉄鉱
条痕色が赤いのが特徴です。

石屋さんでよく売っているヘマタイト。実はヘマタイトの正体は赤鉄鉱なんです。知りませんでした。確かに条痕色は赤色です。磁力はつかないはずなのですが、お店で売られているものは人為的に磁力をつけてられていることがあるようです。
③黄鉄鉱

金色でサイコロ型の結晶を作ります。金みたいでカッコいい♩

条痕色は黒色でした。
こちらは結晶の小さな黄鉄鉱。うーんミステリアス。
④黒雲母

薄く剥がれる性質をもちます。黒雲母はテカリ具合といい海苔に似てます。
硬度が低く釘で簡単にキズをつけることができます。


同じ雲母でもこちらは白い白雲母。

条痕色は黄色でした。

層構造がわかりやすいです。
⑤孔雀石

銅を取り出す実験で使った孔雀石。
条痕色は緑色です。

100均で売られています。今度、この孔雀石から銅を取る実験をしてみたいですね。
⑥磁鉄鉱

磁力を持つ石として有名です。

磁石に強く惹きつけられます。

形が変わってもちゃんと磁力をもちます。
⑦ザクロ石

柘榴石といわれてピンとこなくても、ガーネットと言われたら聞いたことがあるのではないでしょうか?
等軸晶系で正12面体構造です。

特徴的な形ですね。
このように赤色のものは宝石として扱われたりします。
⑧方解石

炭酸カルシウムでできています。白くて三者晶系です。

モース硬度は3と柔らかめです。

このように透明なものは光の屈折に使われます。

方解石を通して見ると光を屈折させて裏側のものが二重に見えます。
⑨正長石

長石の一種です。単斜晶系。カリ長石と呼ばれています。

火成岩の含有鉱石で無色鉱物です。花崗岩や流紋岩に多く含まれています
⑩角閃石

正長石と同じ火成岩の含有鉱石です。こちらは有色鉱物。


11、方鉛鉱

名前の通り鉛が含まれています。この鉱石から鉛を取り出してきたそうです。
12、滑石(蝋石)

昔はこれで道に落書きをしていましたね。爪で簡単にキズをつけられるくらい柔らかいです。

四角く加工したものは蝋石として売られています。

チョークみたいですね。
13、ホタル石

見た目がとても綺麗です。薄い緑色をしていました。
正八面体です。ミョウバンの結晶に似てます。
条痕色は白色でした。

ブラックライトに当てると発光します。ホタル石の名前にふさわしいです。
岩塩

塩化ナトリウムの結晶だとわかりませんでした。方解石だと思ったのですが文字が重ならず、石英の結晶構造は見えない。よく見ると劈開が観察できるので塩化ナトリウムとわかるそうです。舐めるのは禁止ですよー。

ということで色々な岩石の鑑定でした。鉱石は石ごとに成分が異なるため色が違ったり結晶構造が乱れていたりと鑑定は本当に難しいです。学者さんはすごいということがわかりました。