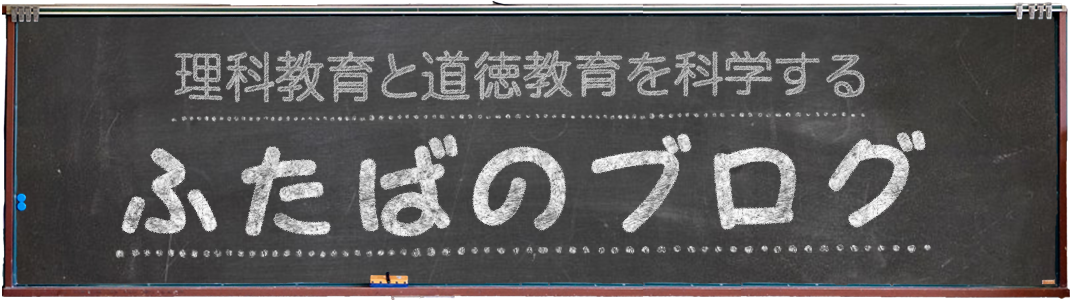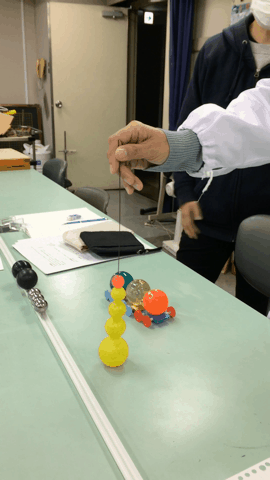大阪の南部地方の地層を観察しました。
大阪南部の地層の観察

出典:wikipedia
こちらは光明池緑地にある露頭です。

白い地層が観察できます。

近づいてみると1メートル近くあります。これは、ピンク火山灰と言われる地層で、なんと九州の火山が噴火して積もった火山灰だそうです。大阪にこれだけ積もるなんて当時の噴火の凄まじさが伺い知れます。

ハンマーで叩いて取り出しました。凝灰岩ですね。

粉々していて、手が白くなりました。火山灰の成分はガラスと同じSiO2。ガラスの粉だったんですね。
地層から取り出した凝灰岩と粘土。それぞれ違った特徴があります。粘土によっても色が異なるんですね。

次に向かったのは和泉市内田町の露頭。

ここではあずき火山灰の地層を観察しました。地学の分野で大きな功績を残された京都大学の市原先生とその奥さんが大阪層群を詳しく調べていた際、とても気温が高く暑かったそうです。その時にこの地層をあずき火山灰と名付けたとか。


茶色い地層を削ると、

あずき色の火山灰の地層が見えてきました。この火山灰も九州から飛んできたそうです。火山灰の地層は鍵層と呼ばれ、日本各地の地層の時代を選定することができます。青森にもあるそうです。
他にも
- この地層には硫黄が含まれていてpHが低く植物が生育できないこと
- 粘土層が海成性の粘土層と地上の粘土層が交互に積み重なっていることから海面の上下があったこと
- 暑い時期と寒い時期(氷河期)が交互にきていたこと
- それが花粉や魚などの生物の化石にも現れていること
などを学びました。恐竜がいたころは現在より10度以上気温が高かったそうです。地球の壮大な物語に頭がクラクラしました。文章のまとまらなさに現れていると思います(笑)

落合橋から見た近木川です。
堆積岩を学ぶ

川にはこのような石がありました。
礫岩

砂岩

泥岩

授業で使えると思いましたが、持って帰るのが大変なので諦めました(笑)
地学は数万年とか数百万年とか規模が大きくでよく分からなくなってしまいそうです。ちなみにあずき火山灰のような1mの火山灰が日本全国に降り積もる火山噴火は100万年に一度程度の割合で起こっているそうです。私たちが生きていけるのはただ、運がいいだけだということを痛感した一日でした。