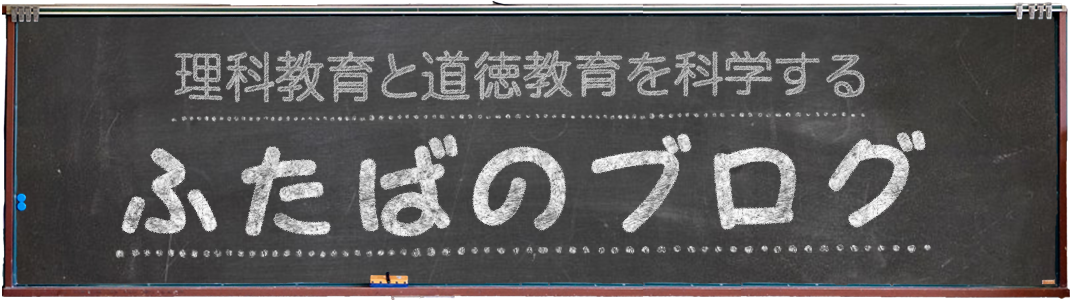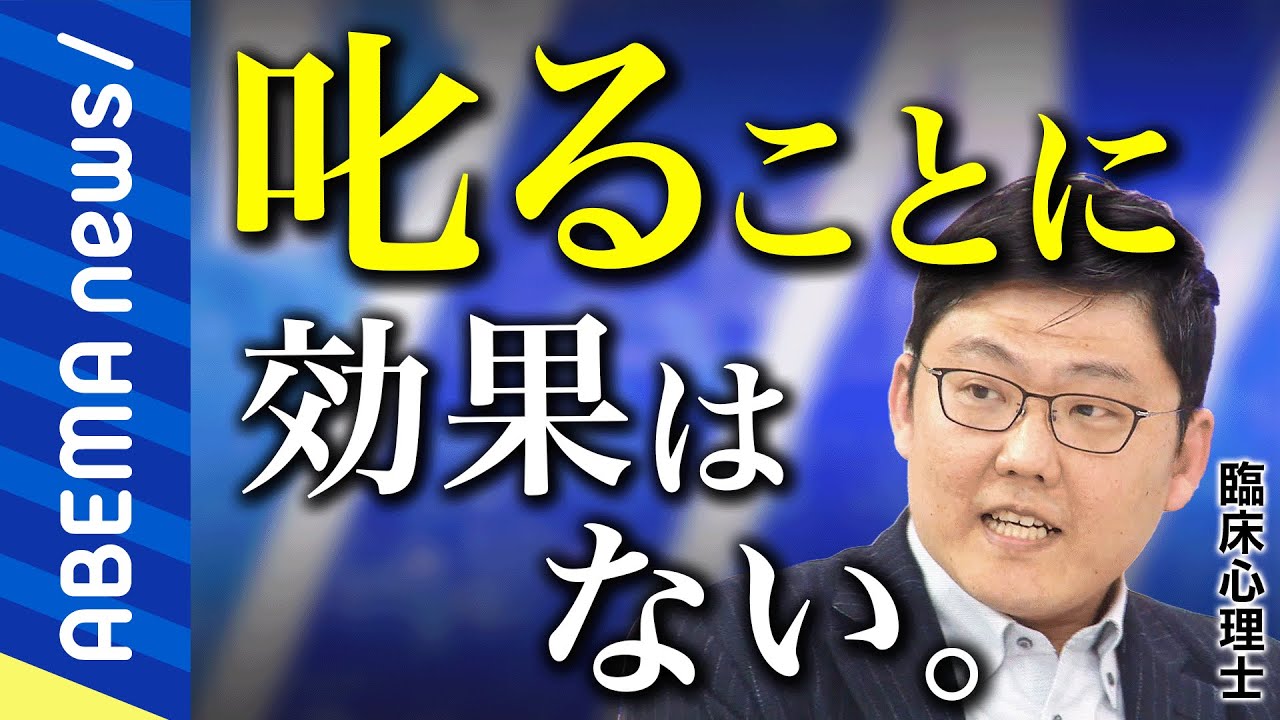今はどうか知りませんが、10年ほど前ふたば初任の頃よく「叱ると怒るは違うんだよ。怒るは感情的に怒鳴るだけ、叱るは冷静なんだよ。」的なことを言われました。その時は「なるほど〜」と納得しました。でも、ある程度経験をつんでから尊敬する先生から「感情的に怒ってはいけないなんて簡単に言うけど、生徒を本当に変えようと思ったら必ず感情が出るはずだし、感情なしに生徒を変えることなんてできない!ロボットに冷静に叱られたとき行動を変えようと思えるか?」といわれて「確かに!」とさらに納得しました。
叱り方と教師
「叱ること」は教師にとって避けて通れない仕事です。同僚教師からみても、「叱り方がうまい=いい先生」と見られます。「授業が上手い先生」より「叱り方がうまい先生」の方が仕事ができると評価されることさえあります。ふたばも叱り方についてはたくさん本を読みました。野口芳宏先生の叱り方の作法はとても勉強になりました。
[itemlink post_id=”21895″]
でも、やっぱりしっくりこない部分も・・・「叱る」ってなんなんでしょうか?そんなふたばに「叱る」の新しい観点を与えてくれる動画をABEMAで見つけました。
叱る依存(叱る=愛情の裏返しはウソ?)
叱ることの意味
この動画を見て、叱ることについていろいろ考えさせられました。
- 叱るという行為には必ず上下関係がある
- 叱る行為は叱る側のニーズを強く満たすため依存性がある
- 叱るのは、相手の行動を変えたいから
- 叱られた相手は叱られることに慣れていくため叱られても行動を変えなくなる⇒叱る側はより強く叱る必要がでてくる
- 叱ることが良しとされるのは危機回避と抑止の2つの場面のみ
- ふたばの感覚では抑止は「叱る」には入らないため実質危険回避のみ
一番なるほどと感じたのが叱ると「気持ちよくなってしまう罠」についてです。
叱る依存(叱ると気持ちよくなってしまう理由)
この動画では
- 自己効力感という報酬
- 処罰感情の充足
- 叱るの強化と慢性化
の3つについて説明されていました。ここではこの3つを教師に当てはめて考えていきたいと思います。
自己効力感という報酬
簡単に言うと教師としての自信を得られるということです。指導に従えば「俺は教師として仕事したぜ」と気持よくなることができます。ふたばはこの気持がよく分かりますし、指導後気持ちよさそうな教師をたくさん見てきました。
処罰感情の充足
教師により強くはたらくのがこの処罰感情の充足。「悪いやつは罰せられるべきだ」という感情が満たされます。教師は真面目な人が多いです。学生時代に生活態度の良くないクラスメイトに困らされた人も多いです。「悪いやつは罰せられる」のは誰でも気持いいです。ふたばも半沢直樹の大ファンです(笑)
叱るの強化と慢性化
行動主義心理学における強化とはある行動が増えることを意味します。教師が「叱る」という行為で成功体験を覚えると「また叱りたい」という思いが強まります。教師なんてさらに「きちんと指導して偉い」なんて褒められたりするんです。強化はどんどん進みます。強化がさらに進むと叱るのが日常になります。これが慢性化です。こんな状態で「できる教師はアメとムチ」なんて言い出したら、DVと同じ構造に見えてきます。
まとめ
「叱る」という行為は本当に難しいです。自分の叱り方は本当に正しいのか考えてもらいたいと思いました。ということで今回は叱る依存についてでした。もっと叱る依存について知りたい方は、村中直人さんの「〈叱る依存〉がとまらない」をぜひ読んでみてください。
[itemlink post_id=”26508″]