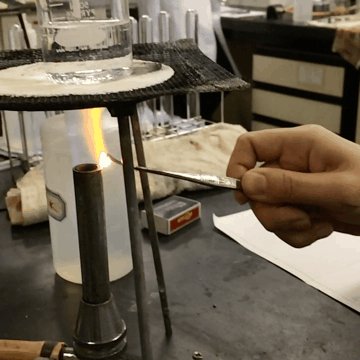社会で習う銅鏡。銅鏡が作られた当時どのような色だったか知っていますか?今回は知ってるようで知らない理科の豆知識についてです。
銅鏡(青銅)をつくる実験

博物館や歴史資料館にある銅鏡は青っぽい色をしています。青銅(ブロンズ)と呼ばれているので青いとおもっている方が多いと思いますが、実際は金色に近かったそうです。
見つかった銅鏡

復元されたレプリカの銅鏡







金色です。
青銅を作る実験
実際に作ってみます。青銅(ブロンズ)は錫と銅の合金です。
すずを20g計りとります。
綺麗ですね。銅も15g計りとります。

白い蒸発皿(青いものは高温で割れる(ことが多いように感じます))で加熱します。錫が溶けてきたら、銅を加えていきます。

高温の液体状態では銅と錫が混ざり合います。

ターミネーターの名シーンを思い出します(笑)

十分に溶け合ったら、手早く金属の皿に移します。下に濡れ雑巾を引くのを忘れないでください。

急冷されて固まった銅と錫の合金。青銅の出来上がりです。
この状態では鏡として使えません。 

紙やすりでひたすら磨き、最後に研磨剤で磨くと・・・
鏡になりました。iPhoneのレンズが写っていることから鏡の役割をしていることがわかりますね。銅と錫の割合を変えることで色を変えたり硬さを変えることができます。
私たち人類の歴史は金属の歴史でもあります。青銅が作られていた時代を青銅時代というほどです。合金は単一の金属ではなし得ない性質を持ちます。いまでも、レアメタルといった希少価値の高い金属に高い値段がついていますね。金属をうまく利用することで人類はこんなに繁栄することができているということがわかりました。